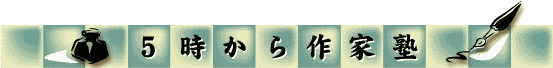| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
8.受付嬢の赤い服
設計部門には、口下手で女性を口説くことができない人間がいる。近田や大久保、桐畑、永沢、……。彼らは仕事に喜びを覚え、それ以外のことには気を使いたがらない。しかし、設計部門に属する人間がすべてそうだとは限らない。口がうまく、頭の中は女性を口説くことでいっぱいな男性もいる。奇数年入社にこのタイプが多いのだが、彼らは勤続年数が増すとともに、本来の理科系な人間になって、エンジニアとして活躍し始める。しかし、なかには、そのままを貫き、遊び通す人もいる。
女性を口説くチャンスを窺ってばかりいる人間と、仕事のことしか頭にない女性が関わりをもつとき、お互いどのような態度を示すのであろうか?
*
「僕の趣味は、肩もみ。あなたの疲れをほぐすのが何よりの喜びなんですぅ〜」
磯子周一は、席にいる女子社員のうしろに立ち、肩に手を当てる。
「くすぐったーい、きゃっ、きゃっ」
女の子は喜んでいるのか、嫌がっているのか。磯子は迷いもなく、女の子はまんざらでもないと思っている、と信じ込んでいる。いつものことながら、腕や背中まで、モミモミ、モミモミ。もう何がなんだか……。
ちなみに彼は、仙台にある国立大学で情報工学を学び、1981年(奇数年)に入社して、以来七年、入社当時のキャラクターを保ち続けていた。
磯子は、昼休みが終わると、機械設計課のエリアに入り、みどりの姿を見つけて近づく。
「小林さん、お昼ご飯はいっぱい食べましたか?」
「はぁ」
「じゃぁ、お腹いっぱい、胸おっぱい、ハハハ」
一人でうけてる磯子に、みどりは冷たい視線を送る。予定では、午後一番でOEM先にクレームの報告書を提出し、新機種の図面を仕上げ、二時からは来年開発予定機種のデザインレビューが入っている。五時からは試作品の問題点についてのミーティングがあるので、それまでに資料を用意しなければならないのだ。
「小林さん。昨日ね、僕は本社で仕事だったんですよ。東京タワーが近くてねぇ……。都会っていいですよね」
「あっそう」
みどりは興味なさそうに答える。磯子の話に付き合い、半日無駄にしたことがあったからだ。磯子は気にも留めず喋りつづける。
「本社の女性はきれいですね。第一、スーツを着ているんですよ。スーツ。ビシッとキメて革の靴を履くと、女性ってそれだけできれいに見えますよね」
みどりは、自分が着ている工場のダサい制服に目をやり、磯子を睨み返したが、磯子は延々と、本社の女性の話をする。
「それから、うちの受付の上野さんって、あの清楚なOL風の制服が似合ってますよね。あそこまで芝通カラーの赤が似合う人はいないですよ。地元の短大を出て、芝通に就職したんですよね。短大っていう響き、僕、好きだなぁ。育ちが良さそうで」
磯子は受付嬢に話題を移す。受付嬢の制服は他の従業員とは違い、銀行員風の上下に、リボン付きの白いブラウス。受付嬢は清楚に着こなしている。
「私は仕事に関係のない人がどうだろうと、どうでも良いことなのです。無駄話はこのへんで勘弁してください」
みどりの言葉に、磯子は不満そうな表情を浮かべ、今ならセクハラものの冗談を言って去って行った。
その夜、みどりの夢に磯子が出てきた。
「受付嬢の制服って、MHデザインのブランド物だって知ってました?」
「しらない」
夢の中でも、みどりはそっけない。
「ところで小林さん、そのドライバー、腰のポケットに入れるのやめたほうがいいですよ。手で持ったほうがステキです」
と磯子は言った。みどりは机の上にあるプラスドライバーに視線を移す。えんじ色のグリップから黒光りしている金属部分がニョキッと伸びている。みどりはドライバーを腰のポケットに差して歩く。ファクシミリのネジを外すときに使うからだ。
「腰のポケットに差して、どこが悪いのよ。余計なお世話。あんたに言われる筋合いはないわよ」
みどりは言い返す。
「あーぁ、可愛くないなあ。受付嬢の上野さんみたいに素直なほうが得なのに。小林さんって、損しているなぁ。それから、上野さんのヘアースタイル、参考にしたほうがいいんじゃないんですか? 小林さんの伸ばしっぱなしの髪の毛、ヘタしたら四谷怪談ですよ」
みどりは忙しくて半年以上も美容院に行っていない。が、そこまで言われるほどひどくもない。
「あぁ、すいません。余計な事を言いました。小林さんはどうせ作業帽を被って仕事をするから関係なかったですね」
磯子はにやけながら言う。みどりは、磯子と喧嘩になるのを避けるように、「ハイハイ」と受け流す。
「それからその作業靴、みっともない歩き方にぴったりですよ」
「みっともない歩き方?」
「ええ、小林さんって、忙しそうに前かがみで歩いてますよ。自分ではわからないでしょ。こういう人とは結婚したくない、ってみんな思ってます」
磯子は捲くし立てた。いつも笑っている顔が今までに見たこともないくらい怖くなっている。
「ちょっと、その言い方ひどくない? だいたい、さっきから聞いていると、受付嬢の上野さんと私を比較して……。私は彼女とは仕事も違うのだから、格好だって違って当然でしょ」
「前から思っていたんですけど、その喋り方、何とかならないですか? なんか、すごく威圧的。いつも電話口で、『早くしてください!』とか、『困ります!』とか、きつい口調で言ってるじゃないですか? もう少し、『ご苦労さまで〜す』とか、可愛らしく言えないんですか? 無理なのはわかってますけど」
もうみどりは言い返さない。腹が立って言葉が出ないのだ。
「それから、この間の残業時間、女の子が全部帰っちゃった後に、管理課にお客さんが来たじゃないですか? 管理の杉本さんが、申し訳なさそうに『女性が小林さんしかいないので、お客様にお茶を出していただけませんか』って頼んだでしょ。僕、見てましたよ。そしたら、小林さんは管理の大宮主任を指差して、『あの辺で暇そうにしている人に頼んでよ。男がお茶淹れちゃあ、いけないの?』って、言ってましたよね。たしかに、大宮主任は暇そうでしたよ。でもねぇ、お茶なんて五分あれば淹れられるでしょ。杉本さんも困っているのだから、助けてあげればいいのに」
「よくもそんな……」
みどりは限界を超している。徹底的に磯子をたたきのめしてやろうと立ち上がる。
すると次の瞬間、二人は裸になって抱き合っていた。磯子がゆっくりとみどりの中に入り体を動かすと、みどりもあわせる。みどりは嫌がるどころか、磯子を受け入れている。やがて、みどりの胸とお腹は二人の汗が混ざり合い、ぐっしょりと濡れ……。
そこでみどりは目が覚めた。汗をかいている。悪夢だ。夢の中とはいえ、磯子に感じてしまった自分を不覚に思う。みどりは汗を拭い、胸や肩を払った。
「僕だって、小林さんの裸じゃ立ちませんよ」
磯子だったらそう言うに違いないと思うと、みどりは余計腹が立った。時計は夜中の二時を指している。みどりは、そのあとなかなか寝付けなかった。
目が覚めると、七時三十分を過ぎていた。いつもより三十分も遅い。みどりは慌てて支度をして外に飛び出す。こういう時に限って、赤信号が多い。信号が変わると、みどりは前の人を押しのけんばかりに、大股で歩き出す。証券会社の大きなガラスに写った自分の姿を見て、歩く姿勢が前かがみになっていることに気づく。
「どうか、昨日の夢が正夢じゃありませんように」
みどりは呟いた。
着替えるためにロッカールームに入ると、受付嬢の上野が入って来た。みどりは普通を装い、挨拶を交わす。上野が制服を手に取ると、後首の裏側にあるデザイナーのロゴがみどりの目に入った。『MH』。
みどりは夢の中で磯子が、受付嬢の赤い服は『MH』デザインだと言っていたのを思い出す。
「もしかしたら正夢かもしれない」
みどりは頭を抱えた。
|