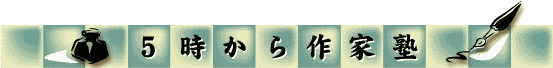| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
7.誰がラブホテルにカップルを閉じ込めたか
世の中には、完璧主義な人間がいる。もちろん、芝通の設計部門にも完璧主義者はひしめいているのだが、人間である以上、完璧にはなれない。細心の注意を払って設計しても、決められた試験をクリアーしてから出荷しても、お客様のところで問題が起きてしまうことがある。今回は、顧客クレーム、「ラブホテル様 激怒」のお話し。
問題が起きたのは開店したばかりのラブホテルだった。派手な外観と最新設備が人気で、けっこう繁盛している。
そのラブホテルに、一昨日初めて利用し、今日は二度目という男女が入った。女の子はボタンを押して部屋を選び、男はキーを取る。部屋に入ると、女の子は枕もとのスイッチをスライドさせて照明で遊び、意味もなく有線放送のチャンネルを変えては喜んだ。男はその横にあるボタンを触って、ベッドが振動する事を伝えた。
することを終えた二人は、「帰るか……」ということになってフロントに連絡しようと受話器を上げる。
「この電話、ヘン」
と女の子は言う。男は受話器を渡してもらい耳に当てるが、何も聞こえない。もう一度、男は受話器を置き直してダイヤルする。しかし、フロントへはつながらなかった。
「まあ、いいよ。部屋を出て、フロントでお金を払えばいいじゃないか」
二人はドアを開けようとした。ところが、ドアは開かない。このラブホテルは、部屋に入ると自動的に鍵がかかる。帰るときはフロントに連絡して、エアシューターでお金を精算すると鍵が開く。防犯と確実な料金回収の為に、このシステムを取り入れているのだ。二人は部屋に閉じ込められたことに気付く。彼女は大声で叫ぶけれど、防音が行き届いた部屋は、彼女の声を外に漏らさない。男はドアを蹴り上げるが、ドアはびくともしなかった。この当時、すでに携帯電話は世の中に売り出されていたが、高価で単行本二冊ほどの重さがあり、持ち歩く人は少なかった。二人は外に出ようといろいろ試してみたが、どれも失敗。
そのあいだ、二人が、「せっかくだからもう一回やっておこう」と前向きになったのか、「この世の終わり」とばかりに萎えてしまったのかは想像にお任せするが、それから数時間後、従業員が故障に気付き、二人は救出された。原因は、芝通製構内交換機の故障。他の部屋も同じようにフロントへの連絡ができず、数組のカップルが被害に遭っていた。
芝通に緊急連絡が入り、数名の人間が現地調査に出向いた。先方はかなりのご立腹である。1988年電子式構内交換機(PBX)の国内販売額は、いわゆる「交換四社」と呼ばれるメーカーが上位を独占していて、芝通はこの分野ではマイナーである。この時期に「信頼性に問題あり」というレッテルを貼られるのは致命傷になりかねない。数日後、関係部門の部課長が揃って丁寧なお詫びをした。
誰がカップルをラブホテルに閉じ込めたのか? クレーム情報が設計部に届くと、担当者は自分の設計ミスかどうか、当たりをつける。自分には関係ないクレームならすぐに忘れ、設計中の仕事に集中を戻すが、はっきりしないときは、ひそかに自分のミスでないことを祈ったりするのである。
構内交換機のクレームは、近田の設計ミスによるものだった。入社四年目の近田に対して、上司は責めなかった。が、原因の究明と、なぜこのような問題が社内で見つからずに顧客のところで出てしまったのか。どうすれば、再発を防ぐことができるのか。近田にレポートをまとめるように命じた。
近田が寮に戻ると、同室の大久保は布団を敷いてテレビを見ていた。テレビはソウルオリンピックを中継していて、カールルイスが走り幅跳びをしているところを映し出す。
「大久保さんがこの近田よりも早く部屋に戻るなんて珍しいですね」
「熱が出ちまった。三十八度なら休まないけどな。ひさしぶりに、ぐっすり眠ったおかげで随分楽になったぜ」
近田は、麦茶を二人分入れ、大久保に渡す。
「近田は、設計ミスをしてしまいました」
空になったコップを眺めながら呟く。
「設計ミス? オレは、衛星通信の電気設計やってるけど、そんなのしょっちゅうさ。引いた図面にミスがあったら、ジャンパーを飛ばすとかすりゃぁ、解決じゃん」
「じゃんぱあ?」
「基板の裏に被覆導線をハンダでつけるんだ。オレが設計した基盤はジャンパー線だらけで基盤の緑色が見えなくなっちまった。おまけに、厚くなりすぎて、ケースに収まらないんだぜ。わかる?」
「よくわかりませんが、それだけミスが多いことと理解いたしました」
大久保はムッとしつつ、うなずく。
「近田のミスで、お客様に迷惑をかけてしまいました」
近田はラブホテルで起きた事件を大久保に話した。
「その構内交換機の故障した部分の設計担当が近田君だったわけだ? それはまずい。けど気にしないほうがいいぜ」
大久保は麦茶をすする。
「調べてみると、ノイズが原因でした」
「何のノイズ?」
「ベッドに仕掛けられた機械が小刻みに振動すると、ものすごいノイズが出るのです。そいつに構内交換機がやられて内線不通になってしまったのです。普通のビジネスホテルで使うぶんには問題ないのですが、あのラブホテルのノイズは普通ではなかったのです」
「……設計している時には予想できなかったんだ?」
大久保は訊きづらそうに言う。
「はい、近田は振動するベッドなんて見た事がありませんでした。ラブホテルというものも今回の調査で初めて入りました。なにぶん、近田は今まで、女性とお付き合いした事がなかったもので……。おまけに、いくぶん頭も悪いので設計している時には予想もしませんでした」
近田は熱い麦茶をついで、ゆっくりとすする。
「オレは近田くんが頭悪いとは思わねーよ」
「そうですか、近田は勉強はできるけれど、頭が悪いとよく言われます」
「確かに、近田君はちょっと変わってるけどよ。それのどこが悪い? 自信持ちなよ」
「ありがとうございます」
近田は残りの麦茶を飲んだ。大久保は布団を敷く。
すると! 壁の向こうから音楽が聞こえる。オフコースの『Yes‐No』のイントロだ。午後十一時三十分。小田和正の透き通った声が薄い壁を突き抜けて届く。隣室の永沢は、仕事が終わって部屋に着くと、オフコースをかける。はっきり言って、大久保はオフコースが嫌いだ! というより、嫌いになったのだ。でも、永沢は先輩だから、大久保は何も言えない。
「『Yes‐No』はいい曲かもしれない。でも、オレは歌詞が許せねぇ!」
大久保は隣りの部屋に向かって大きな声で言う。
♪君を抱いていいの 好きになってもいいの〜
永沢は、オフコースをかけ続ける。
入社した頃の大久保は、共同生活なのだから多少のことには目をつぶらなくてはいけない、と思っていた。しかし、ある夜――。大久保は、「また、オフコースか……」と聴いていたとき、
<YesかNoかなんて、彼女にいちいち訊かずに、トットとヤッちまえばいいじゃん>
と俄然思ったのである。付き合い始めた彼女にお伺いを立てる殊勝な男を蹴飛ばしてやりたい、そういう気分だった。それ以来、『Yes‐No』を耳にすると、どうしても小田和正にツッこんでしまう。
♪今なんていったの 他のこと考えて〜
「なにぃ? いやらしいこと考えてないで、ちゃんと人の話を訊けよ。頼むぜ、小田和正!」
という具合である。
♪好きな人はいるの こたえたくないなら きこえないふりを すればいい〜
「なにぃ? 答えなくてもいいなら最初から訊くな! 頼むぜ、小田和正!」
♪君を抱いていいの〜
「なにぃ? いちいち訊かずに……」
「以下省略!」
大久保は、薄い壁の向こうにいる永沢に聞こえるようにオフコースをこき降ろす。しかし、永沢は動じない。『さよなら』が始まる。大久保は壁を蹴り上げた。
♪さよなら、さよなら、さよなら もうすぐ外は白い冬 愛したのはたしかに君だけ〜
毎晩、オフコースは続く。
しかし、永沢のおかげ?で大久保は、オフコースなら十曲以上、歌詞を見ずに唄えるようになった。ちなみに、みどりはオフコースが大好きなのだ。
「君を抱いていいの? なんて言われてみたーい」
みどりは、カラオケボックスで、嫌がる大久保をよそにオフコースを唄う。
「オフコースはやめてくれ〜」
大久保はそう言いながらも、みどりにあわせて口ずさむのであった。
♪愛したのはたしかに君だけ そのままの君だけ〜
|