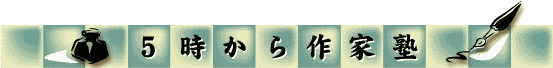| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
3.鋭い直感、鈍い直感
日々の生活の中で何かを選ぶとき、どのようにして決めるのだろうか。洋服を買う時、靴を選ぶ時。候補をあげて試着して、迷いながら決める。仕事も同じで、例えば、外注業者を決定するときには、価格、納期、スキルなどを比較検討して決定する。
芝通で決断までの時間がおそろしく短い人といえば――桐畑。
「はい、それはこうしたほうが、いいですね」
条件さえ揃えば、答えが出るまでに三秒以上時間をかけることはない。鋭い直感が働くのだ。開発中の桐畑が、霧の中を手探りで前に進むようなとき。
「桐畑さん、無理なのでは……?」
「そんなことはありません」
桐畑は、腕を組み約三秒動きを止める。すると……、あら不思議! 桐畑は、「そうか」と呟き、直感的に実現可能だとひらめいた方向に進みだす。一瞬のうちに、無数にある条件を捉えて行動を起こす姿は、野球選手が剛速球をホームランにするのと似ている。
そのような桐畑なので、就職先を芝通にしたのも直感だった。人に訊かれたら表向きの理由を答えはするが、決定的な理屈はない。給料や会社の将来性を比較して決めたわけでもないし、家族や教授の意見を尊重したわけでもない。実のところ、桐畑は、これまでの人生を直感でくぐり抜けてきたのである。では、みどりはどうであろうか。
みどりが芝通に決めたきっかけは、大学四年の六月のことだった。
「去年、芝通に入社した川島直子さんから連絡があったので会ってみませんか」
教授の佐藤はみどりに告げた。不景気な今では考えられないが、新人採用のため、新入社員が母校と連絡をとり、足を運んだ時代である。佐藤の後ろ側にはデスクが並び、助手が論文に目を通している。ドイツの大学院で博士課程を修了し、学位も取得しているせいか、ドイツ語で電話していることもある。独身で千葉県に住んでいることは知られていたが、助手のプライベートは謎だった。みどりは助手にアドバイスを求めようと視線を送るが、彼は論文から目を外さない。近寄りがたくて隙がない。研究には妥協をしない完璧主義。おまけに、やはり直感が鋭い。
「とりあえず会ってみたらどうか」
と教授は言った。
一週間後、みどりは大学の近くの喫茶店で川島と会った。
「好きなものを頼んでね。会社からお金が出るから遠慮しないで」
みどりはパフェを頼む。川島は、芝通について語った後で、
「芝通の工場を見学しませんか?」
と言う。みどりは断る理由もなく、首を縦にふった。
「工場見学っつーのは、面接試験の意味合いもあるんだぜ」
研究室に戻ったみどりは、クラスメートに言われてびっくり。しかし、「まっいっか」と約束の日、工場見学に向かうのであった。
数日後、芝通の担当者から教授に、「内々定……」というような意味合いの連絡が入る。就職協定があった時代、露骨に「合格」とは言いにくいのであろう。
みどりが訪問した会社は、芝通一社だけだった。理科系の学生は、学校推薦制度――うかったら、その会社に入社するのが前提――で就職をきめる人が多いので、珍しいことではない。1984年夏、あっけなくみどりの就職活動は終わった。
桐畑が取扱い説明書の仕事をみどりに任せたのは、桐畑なりの計算はあったが、まずは直感で「いける」と判断したからだった。新人や女性には仕事を任せないという人もいた芝通で、はたして桐畑の直感は正しかったのだろうか?
みどりは取扱い説明書の構成を考えていた。新入社員なら、少しでも早く一人前の仕事をさせてもらいたい、と思うものである。みどりはドラフターに視線を移す。手描きが当たり前の時代、桐畑が図面に向かっている。
<せめてドラフターに触らせてくれ〜>
みどりは桐畑を見つめる。と、その時、桐畑が席を立ち、みどりの席に向かう。
「実験室に来てください」
みどりは胸に期待を抱き、桐畑の後をついていくと、そこには来月量産開始予定機種「Z25」の試作品があった。
「記録紙カバーの開閉試験をやってください」
「Z25」は記録紙を交換するときに、後方にあるボタンを押し蓋を開ける。次の機種に買い換えるまでのあいだ、何回も記録紙を交換するわけだが、ボタンが壊れて蓋が閉まらなくなったら、ユーザーはクレームをつけるであろう。試作品で、カバー開閉試験をクリアーすることも量産開始条件のひとつなのだ。
みどりが指示されたことは、ボタンを押して、蓋を開けて、閉める。それだけだ。しかし、三百回あまりの繰り返し。
「大学まで出て、安い給料で、こんなつまらないことをさせられるなんて!」
バタンッ。
もう、二時間も単純作業を続けている。
「こんなはずじゃなかった」
バタンッ。みどりは独りごとを言っているうちに、蓋を閉める手に力が入る。荒々しい音が実験室に響いた。
「あと何回で終わりますか?」
桐畑が実験室に姿をあらわす。
「あと三十回です。……あのぉー」
「かなり強く開閉しましたね。でも、壊れてない。ヨシッ」
桐畑の頭の中は、「Z25」のことで一杯なのだ。
「取扱い説明書は、でき次第見せてください」
桐畑はそう言うと自分の席に戻って行った。
みどりは、取扱い説明書に向かうたびに、こんな所でこんなことをしていていいの? という気持ちが大きくなっていく。外注業者に、イラストや文章を任せるための指示書を送る。みどりが苦手とすることばかり。どうせ仕事をするなら得意なことをしたい。
「家に帰ったら、就職情報誌を買ってやる!」
景気が良いので、職はすぐに見つかるだろう。
こうしてみると、やはり、みどりが直感で決めたことは、良い結果をもたらさないのだ。要するに、みどりの直感は鈍いのである。みどりは桐畑に「辞めたい」と伝えるチャンスを窺っていたが、仕事以外のことを話す隙が桐畑にはない。
「とはいっても、任された仕事はきちんとやらねば……」
期日になり、みどりは取扱い説明書を終わらせ、桐畑の机の上に置く。すると一時間後、みどりの机にポストイットが貼られまくった取扱い説明書がのっていた。桐畑はたった一時間で、指摘事項をまとめたが、どの指摘も,尤もなものだった。学生時代の桐畑はどの科目もまんべんなく優秀で、もちろん国語も成績がよかったわけで、私立理科系しか行く所がなかったみどりとは違うのである。しかし、桐畑はそのことを誇りに思ってもいないし、みどりを馬鹿にしているわけでもない。
「取説は商品の一部です。ですから、瑕疵があってはならないのです」
加えて完璧主義。
「桐畑さんって、A型ですか?」
「それがなにか?」
私はそういうものには興味ありません。と、桐畑はメガネを外して左の人差し指で目頭をこする。
桐畑は隙もなく、完璧主義で、厭味な感じすら漂う。見た目は普通なのに、ちょっと変わっている。が、桐畑を苦手としている人はいない。
設計部門の人間が苦手にしている人物といえば――。品質保証課の雛形である。
ある日の午前中のことだった。
「昨日出した、試作品の問題点、どーなってんだい?」
雛形は機械設計課に入ってくるなり、机に座っていた桜井に向かって怒鳴る。日野も桐畑も席にいない。まだ寝ぼけていた桜井だったが、体をしなつかせながら
「どーもすいません」
と笑ってごまかす。
「最近の機械設計はたるんでんなぁ」
雛形は桜井たちのことを責めなじり、去って行った。
「昨夜遅くにもらった問題点が、朝イチで解決するわけないでしょうがッ」
桜井は、雛形の背中に言葉を吐き捨てる。もちろん、本人に聞こえないように。雛形は気付かず、次は電気設計課に入り、同じように怒鳴り散らし、席に戻って行った。納期を優先したい設計と品質を優先したい雛形。考えてみれば、対立しないほうがおかしい。
ともかく……、取扱い説明書は無事に仕上がった。やはり、桐畑の直感は鋭くて正しい、ということだけは確かのようである。
|