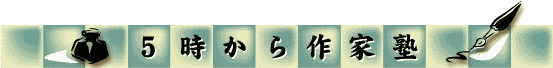| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
10.猛女の記憶と失われた偏見
その後のみどりと祐子はというと――。
明けた月曜日の午前中、みどりが荷物の整理をしていると、祐子がしゃがれた声をかける。
「四月からソフトウェア設計課に異動するんだって? さっき村上君から聞いてびっくり」
「あのぉー……、そのことは金曜日に話したけど、もしかして覚えていないの?」
みどりも枯れた声で答えた。
「えっ? うそ! しらなーい。みどりちゃんと飲んでいるときに、佐久間君が横にすわったところまでは、なんとなく覚えているんだけど……。その後の記憶があやふやなのよ。気がついたら自分の部屋だったの。どうやって帰ったか覚えてないのよ。私ねぇ、喉が痛いんだけど、なんでかな?」
<それは、怒鳴り散らしたせいか、唄いまくったせいか、そのどちらかでしょう>
「それから、ちょっと気になってることがあるの」
「なに?」
「今朝、佐久間君に、おはようって声をかけたの。なのに佐久間君たら、私と目を合わせようとしないのよ。怖がっているようなかんじ。気のせいかもしれないけど……。私、佐久間君に何かしたかしら?」
「いっ、いや別になにも……。気のせいじゃないの。たぶん」
祐子は不思議そうな顔をしていたが、
「ソフトウェア設計課でもがんばってね」
と言い残し、自分の席に戻って行った。
ついに、異動の日が来た。みどりはダンボール箱を台車に乗せてソフトウェア設計課まで運ぶ。
「小林さんは、ここのグループでお願いします」
課長の和田が紹介した上司は、なんと磯子だった。磯子は、隣りの席の人間と喋っている。みどりに気付くと、おきまりのセクハラ系の冗談を口にし、ひとりでウケて笑う。思わずみどりは眉根を寄せる。みどりにとって、何もかもが悪い方へ進んでいるのだ。こういうときは、自分の意思で行動しないに限る。嵐が去るまで、身をかがめているのが一番。
「なにか?」
磯子が尋ねる。みどりは首を横に振り、席についた。
みどりは、機械設計課では家庭用のファクシミリを担当していたので、オフィス用のものを担当している磯子とは一緒に仕事をしたことがなかった。ファクシミリといっても、家庭用からファクシミリシステムまで、さまざまで、百五十名以上の人間が開発・設計に携わっている。自分の担当には詳細な知識があるが、少しでも外れると全くわからない。
「同報送信と中継同報送信の違いも知らないなんて、そりゃひどい!」
<磯子! てめーは、私に喧嘩売ってンのか!>
みどりはグッとこらえて、指示どおり、過去に開発された機種の設計書を読むことにした。
みどりは、手書きの設計書を小脇に抱え、机の上に広げる。そのなかに、ひときわ癖のある読みづらい文字でかかれたページがある。設計者の欄には、磯子の判が押してあった。みどりは目をこらして読む。重要な機種のソフトウェアの取りまとめ役を、磯子は入社六年目で任されている。磯子がかなり仕事のできる人間だということを、みどりは初めて知った。
昼休み、みどりは喫煙室で声をかけられる。振り向くと、「シンシツ保証課、課長のシナガタ」だった。「新しい職場はどうだ?」と訊かれ、みどりはあいまいに返す。雛形は、タバコに火をつける。
「いままで、いくつかソフトウェアの設計問題があったけど、一番印象に残ってるのはなぁ、Z21という機種で起きたやつだ」
まるで戦後の苦労話のように、雛形は同じ話を繰り返すのだが、みどりは愛想よく耳を傾ける。
「小林さん、よく心しときな。ソフトウェアは大きなバグを出すと、出荷した全部に同じ問題が起こるんだよ。機械設計みたいに、部品のばらつきなんてぇものはないんだな。バグがでる時は、全数同じだ。だから怖い。全国規模の回収作業となると、億単位で損失が出るから気をつけんだね」
雛形は煙を胸奥まで吸い、吐き出す。品質には厳しいが、問題が発生していないときは、娘のようにみどりに接する。
雛形の話によると――。1984年2月29日、芝通のサービスセンターの電話は鳴りっ放しだった。「ファクシミリの時刻指定送信ができない」というクレームが続いた。2月28日までは大丈夫だったのに、2月29日になったら、送信できなくなったのだ。ある担当者は、原因を調べていくうちに自分の設計した箇所にソフトウェアのバグがあることに気付く。設計したときに、うるう年の2月29日を考慮し切れていなかったのだ。四年後の2月29日も同じ不具合が起きる。担当者はプログラム修正をして、クレームを寄せたお客様の事務所を訪れ、問題の古いプログラムが書き込まれているROMを回収し、新しいものと交換する。
さらに不幸は重なった。今の時代では考えられないが、プログラムのロックによりモーターが回転し続け発熱するという問題も発生した。技師長、部課長が集まり、ROMの全数回収交換を決断する。クレームが発生していないユーザーに対しても、今後を睨んで回収することになった。
「お前のミスで、この機種の儲けが吹っ飛んだ」
心ない人は担当者に嫌味を言う。なかには何も言わず、目で蔑む人もいた。主任の鈴木は「気にするな」と声をかける。恐らく鈴木も上司として相当責められているはずである。鈴木は重ねて言った。
「気にしても何にもならない。受け止めて流せ」
回収作業は夏まで続く。ミスをした当の担当者も、肩に背広を下げて、全国のユーザーをまわる。
「ファクシミリのメンテナンスにきました」
何も知らないユーザーにソフトウェアのバグがあったことを話して、芝通の製品のイメージを悪くすることはできない。当時の回収作業は、メンテナンスのふりをしてROMを交換し、次のユーザーに向かうという形をとった。(もちろん、今の時代ではこのようなやり方はしない。)
担当者は、あるビルの前に立つ。幅の狭い雑居ビルだ。「加賀里興業」という札がかけられており、黒くピカピカに磨き上げられたベンツが路上駐車している。今までまわったところとは、雰囲気が違う。一階の入り口のくもりガラスには、くもの巣のような放射状のヒビが入っていて、ガムテープが貼ってある。担当者は、ヒビが入った原因を想像すると、帰りたくなった。どうみても、暴力団の事務所にしか見えない。
事務所のドアを開けると、組長らしい人が、机の上に足を乗せ、タバコをふかしていた。その横には、派手でセンスの悪いスーツを着た長身の男と、背の低いパンチパーマの男がいた。
「ファ、ファ、ファクシミリのメンテナンスにいらっしゃいました」
担当者は、丁寧に挨拶するものの、言葉が裏返っている。
「やぁ、ごくろーさん」
パンチパーマの男が愛想よく答える。目つきは悪いが、意外とやさしい。担当者はバッグを開け、ドライバーを出す。
「なぁ、にいちゃんよぉ」
「な、な、なんでしょうか」
担当者は、手が震えるのをどうしようもできなかった。
「このファクシミリは、写真も送れるって聞いたけど、ほんと?」
「はい、このボタンを押して中間調という写真専用のモードにして送っていただければ、大丈夫です」
「ファクシミリっつーのは、香港からも送れるんかい?」
長身の男が口を挟む。
「はい、世界中、電話回線がつながっているところなら、たいていは……」
「そっか。今度、香港から写真を送ってもらおう、なぁ」
パンチパーマの男はうなずく。どんな写真を送ってもらうつもりなのだろう?
「ところでさぁ。こないだ、よそから送られて来た写真、ひでーのなんのって。黒くなっちゃって、よく見えねぇの」
口調は穏やかだが、威圧的な態度。担当者は「確認したいので、その画像を見せてもらえますか?」と言おうとしてやめた。いかがわしい写真を見てしまったら、帰してもらえないかもしれない。画質の問題は、記録画を見れば、原因の当たりはつくのだが。
「恐らく、送信側で中間調モードにしていなかったのではないでしょうか?」
こういうときは、相手側の他社ファクシミリのせいにして、芝通には問題がないことを強調するに限る。パンチパーマの男は、さらに細かいことを訊きたそうにしていたが、担当者は、振り払うように急いでネジを締め、動作確認も適当に事務所を後にした。
そして、担当者は秋が終わった頃、元の仕事に戻ったのであった。
これが、「Z21」で起きた回収事件だった。それ以来、ファクシミリでは、回収するほどの大問題は発生していない。
みどりは、席に戻って「Z21」の初期設計書を探し席で開く。「時刻指定送信」のページをめくる。すると――、癖のある文字で書かれたページが目に入る。設計担当欄には、磯子の判があった。問題を起こして責められた担当者というのは、磯子だったのだ。磯子は後の機種で結果を出すしか、乗り越える道はなかったのだ。陽気に振舞っているが、いつも心のどこかに、このときの辛さを抱えているはずだ。
みどりは何も知らなかった。このとき、みどりは疎ましく感じていた磯子に対して、見方を変えたのであった。
|